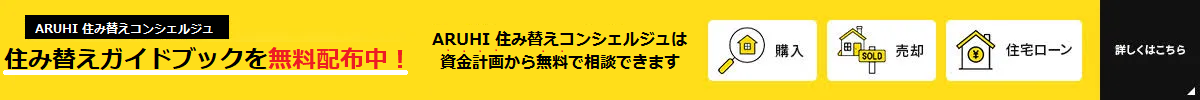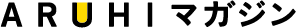アジア最大級の国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア (SSFF & ASIA)が展開している、短編小説公募プロジェクト「BOOK SHORTS (ブックショート)」とARUHIがコラボレーションし、2つのテーマで短編小説を募集する『ARUHI アワード2022』。応募いただいた作品の中から選ばれた10月期の優秀作品をそれぞれ全文公開します。
東京で一人暮らしをしている息子の洋介が結婚することになった。
38歳での結婚は決して早い方ではないが、早く身をかためてほしかった私としては、万感の思いだ。
ただ、相手の女性が、息子よりも14歳年上の52歳だと聞いたときは心の底から驚いてしまった。
洋介に尋ねると、彼女は結婚経験がなく初婚だという。晩婚化が進んでいるとはいえ、50歳代で初めて結婚する女性は少ないのではないか。
わが香取家にとってめでたい出来事だというのに、妻の芳子の顔は曇っていた。洋介の結婚を祝福している様子には見えなかった。息子から結婚相手の年齢を聞いた瞬間、芳子の顔が青ざめたのだ。まさか、といわんばかりの表情で。
ふたりきりでの夕食のあと、私は妻に疑問を投げかけた。
「俺たちが手塩にかけて育てた息子が結婚するのに、なんでそんな顔をするんだ」
芳子は流し台に逃げてしまった。ガチャガチャと音を立てながら乱暴に皿を洗いはじめた。水のしぶきが床に飛び散っている。
「良蔵さん。わたし、素直に喜べない」
キッチンシンクの前で、私に背を向けたまま言った。
「なぜだ」
「だって――お嫁さんが52歳では、孫は期待できないから」
そういうことか。芳子は死ぬまでに一度は孫の顔を見たいと私によく話していた。
妻ほどではないかもしれないが、孫をほしいという気持ちは私にもある。同世代の友人や知り合いのほとんどに孫がいるし、ひ孫が生まれた元同級生もいるくらいだから。
50歳代で子供ができる可能性は低いだろう。だけど結婚相手の年齢で息子の結婚を反対するのは筋違いだ。そんなことは絶対にできない。ふたりが幸せならば、お互いの年齢などどうでもいいのだ。
実は私たちも結婚が遅かった。
私たちは今年で結婚40周年になる。同じ年の芳子と結婚したのは38歳のときで、今では珍しいお見合いだった。一粒種の息子が生まれたとき、私たち夫婦は40歳だったのだ。とはいえ、洋介の婚約者と比べてひとまわりも若かったのだが。
来週の土曜日に、洋介が、結婚相手をわが家に連れてくることになっている。
「まずは、婚約者がどんな女性か見てみようじゃないか。結婚を賛成するか反対するかは、それから判断しても遅くはない」
適切な助言をしたつもりだったが、芳子は泣きそうな顔をしたまま寝室に引きこもってしまった。しょうがないヤツだな。私はソファーに腰を下ろして、ふーっとため息をついた。
わが家の居間に4人もの人間が集まるのはいつ以来だろう。
「はじめまして。佐倉真奈美と申します」
テーブルをはさんで私の前に座った白いワンピース姿の女性は、輝いていた。
若い――それが第一印象だった。色白で顔にしわがひとつもない。52歳に見えなかった。本当は30代なのではないかと勘繰ったくらいだ。
真奈美さんは物怖じしない性格なのか、ハキハキとあいさつした。私の方が緊張してしまい、声が出なかったくらいだ。
私の隣に座る妻の芳子はむすっとした表情でうつむくだけだ。真奈美さんの隣に座る洋介も緊張しているのか、体を小さく揺すっていた。
私が場を仕切るしかない。だがこういう場は初めての経験で、何を話してよいのかわからなかった。
「まだまだ未熟者で至らない息子ですが、よろしくお願いします」
震える声でそう告げるのが精いっぱいだった。
真奈美さんはニコッと笑った。
「温かい家庭を築きたいと思っています。こちらこそ、よろしくお願いいたします」
見た目では判断できないが、頼りがいがあって、洋介を引っ張っていってくれそうな気がした。息子にぴったりの女性かもしれない。
真奈美さんがチラッと芳子の方を見た。しかし、芳子はふくれっ面を私の方へ向け、彼女と視線を合わせようとしない。
「芳子。おまえからも、真奈美さんにひとこと、あいさつをしなさい」
声をかけたものの、芳子の口が動く様子はなかった。ふたりの前で叱るわけにいかず、私はイライラするだけだった。