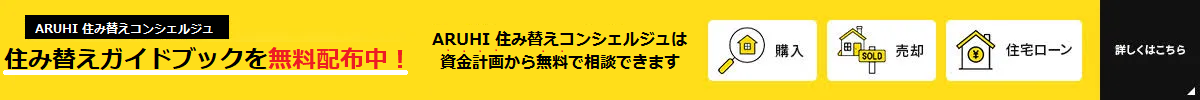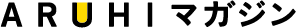アジア最大級の国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア (SSFF & ASIA)が展開している、短編小説公募プロジェクト「BOOK SHORTS (ブックショート)」とARUHIがコラボレーションし、2つのテーマで短編小説を募集する『ARUHI アワード2022』。応募いただいた作品の中から選ばれた9月期の優秀作品をそれぞれ全文公開します。
「ここが、新しい家だよ」
父の紺(こん)介(すけ)がそう言うと、双子のココとリリは「きゃー!」と声を上げて一気に家の中に飛び込んだ。「こらこら、ダメよ」と言う母、穂子(ぽこ)の表情はにこにこ顔で、怒っているのかいないのか、いまいちよくわからない。
紺介はやれやれと肩を竦める。
(けれど、気に入ってくれたようで良かった)
紺介達今田(こんだ)一家は、長年住み慣れた土地を離れてこの街に越してきた。引っ越しの理由は土地開発だ。紺介の父の父、そのまた父の代から受け継がれてきた土地だったのだが、時代の波には逆らえず、泣く泣く土地を手放した。
そしてやって来たこの街は、紺介達が以前住んでいた場所と違って、自然が少ない。けれど、人が多ければ店も多く、その辺はうんと便利になった。長年受け継がれてきた土地を手放す形でここへ来たけれど、これで良かったのかもしれない、と紺介は思う。科学技術が発展した今の世の中で、そういったものに触れることも、子供達の為になるだろう、と。
「そうですよ、悪いことばかり考えたって、お腹は膨れませんよ」
子供達が寝静まった夜中、酒とおつまみを準備していた穂子がそう言った。
「私達はきっと早くに死んでしまうけれど、ココとリリはまだまだ生きていくんですから。沢山のことを知って、色んなことが出来るようになるべきです。それが、あの子達の為です。だから、もう過ぎたことをくよくよ言うのはやめましょうねぇ。それより、今日のご飯の感想とか、明日のご飯のリクエストとか、そういうことを言ってくれる方が、私は嬉しいですよぉ」
「ふふ、それもそうだな」
穂子のほわほわした笑顔に、紺介も笑みを零す。
不安も不満も、完全に無くなったわけではないが、愛すべき家族がそこにいる。
(頑張ってみるか)
言葉にはせず、胸の中で改めて自身を鼓舞する。そして、二人きりの晩酌を楽しんだ後、紺介と穂子も眠りについた。
「行ってきます」
「パパ行ってらっしゃい!」
「らっしゃーい!」
ココとリリの声に送り出され、紺介は家を出た。会社まではそう遠くないので、徒歩で向かう。
紺介を送り出した後、穂子は、小学一年生の双子を連れて学校へ向かう支度をする。新しいランドセルを背負った二人は、朝から元気にはしゃぎ回っていた。穂子がパンパンと手を叩くと、ようやくココとリリは大人しくなる。
「さあおチビちゃん達。これから、あなた達の新しい学校へ行くわよぉ」
「新しいがっこー!」
「がっこー!」
「忘れ物は無いかしら?お名前ちゃんと言えるかな?お友達と仲良く出来る?」
「出来るよ!」
「出来るよ!」
「よろしい、良い子達ね。じゃあ、学校へ行きましょう。お手々、しっかり繋いでね」
「はーい!」
「はーい!」
支度を済ませて、子供達と共に新しい小学校へと向かう。小学校は街の中心部にあり、既に授業が始まっているであろう教室からは、子供達の賑やかな笑い声が響いている。
ココとリリを担当の教員に預けた後、穂子は校長室でこれからの学校生活について一通りの説明を受けていた。
「まあ、行事等は他の学校と大きく変わることはありませんし、お子さん達の様子を見るに心配されるようなこともないかと思いますよ」
「そうですかねぇ、何せ田舎育ちなもので…前の学校では開放的な面が強くて、こういう都会の学校に慣れるのは時間が掛かるかもと思っていたんですけど…」
「何、子供程柔軟な生き物はいませんよ。我が校も、全校を挙げて子供達を支えていきますし、大丈夫です」
人の良さそうな校長に言われ、穂子は「それではよろしくお願いします」と頭を下げ、校長室を出て行く。帰り際にちらりと我が子達の教室を覗くと、ココとリリはすっかり教室に馴染んでおり、他の子供達と仲良さげに話していた。
校長の言う通り、心配する必要は無さそうだと思って、穂子は学校を後にした。