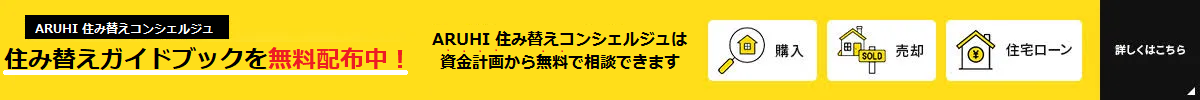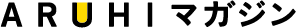アジア最大級の国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア (SSFF & ASIA)が展開している、短編小説公募プロジェクト「BOOK SHORTS (ブックショート)」とARUHIがコラボレーションし、3つのテーマで短編小説を募集する「ARUHIアワード」。応募いただいた作品の中から選ばれた優秀作品をそれぞれ全文公開します。
久方ぶりのおふくろの味は、化学調味料の味がした。
日曜の昼、母がよく茹でていた袋麺。こってりとした味噌の風味は、店で食べるそれと違い、安っぽい。だが僕は母を責める気にはならなかった。この一ヶ月で、僕は身をもって自炊の面倒くささを知っていたからだ。
作家を目指す傍ら、食い扶持を稼ぐ為に就職、そして上京。初めての一人暮らしを始めた僕を待ち受けていたのは、一週間だけ持続した猛烈なやる気と、その後三週間を支配する熾烈な倦怠感だった。意気込んで炊飯をしていた頃が微笑ましいほど懐かしい。今ではレトルトパックのご飯の中に、直接卵を投じて洗い物をゼロにする食事を汲々と行っている。
慣れぬ仕事に忙殺される日々。そんな折に僕は袋麺を食した。ここ最近、ご飯の容器とカット野菜の袋のみが並んでいた食卓に、突如降臨したラーメン丼ぶりの姿はまさしく圧巻だった。その大きな器は、自分で買った丼ぶりではない。隣人が酔った勢いで購入したという丼ぶりを、一つ譲り受けたのだ。そのすり鉢的な形状によって、食器棚に入れるにもやたらとスペースを食うこの代物を、一度も使わずに仕舞うのは癪に思われた。そうして、僕はスーパーの袋麺を一つ手に取ったのだ。
果たして食したラーメンの味は、冒頭に記した通りである。実家に居た頃は何の気なしに食べていたが、改めて味わってみればあまり美味ではない。付け加えるなら、袋麺にはパッケージにあるような多様な具材が入っているものと思っていたが、そうではないらしかった。僕は具材のない実直なラーメンとスープに対し、美味しくないと思った。そしてもう二度と食べることは無いだろうとも思う。そうして、四度目となる孤独な日曜の昼が過ぎた。
あれから一ヶ月が経つ。ようやく研修が終わり、ラーメン丼ぶりは棚の高い位置へと収納された。麺を茹でていた鍋は、コンロの同じ位置で寄せ鍋を作り続けている。寄せ鍋のコストパフォーマンスの良さに着目したのは、僕がこの一月で発揮した最高の閃きであった。
その土曜日の夜も、僕は寄せ鍋の白菜と豚肉を摘まみながら、新しい本を読んでいた。苦手な恋愛描写を克服する為に買った、とあるラブコメ小説だ。休日に一人、鍋と対峙しながら読むものではない。しかし、その小説の一か所に、どういう因果か山の中で味噌鍋を食らう男の描写がある。
男は味噌職人の実家を持つ高校生で、主人公と同い年のライバルだ。共にヒロインを射止めようとするも、自らの不器用さに悩む大男である。そこまではシンプルだったが、問題は本の中盤にあった。冬休みの暮れ。彼が、己の不甲斐なさに耐え切れず山籠もりを始めるのだ。ヒロインも主人公もそっちのけである。誰も助けになど来ない。笹の葉と広葉樹が支配する夜の山林で、彼は一人、自分の心と向き合い続けていた。そして腹が減ると、やおらに辺りのキノコをもぎ取り、持ってきた鍋に味噌を入れ、焚いた火で煮込み始める。そうして彼は、実家の味噌鍋の味わいと、自分の作った鍋とを比べ、自分は一人では生きていけないという現実に向き合うのだ。そこから、己の不甲斐なさを許した彼の快進撃が始まる。
僕は本を閉じ、彼はなんと格好が良いのだろうと思った。実家暮らしの高校生の癖に、山に籠り火を焚いて野宿するのだ。彼は間違いなく強い。だが、その強さには慢心せず、むしろ弱さと向き合って戻ってくる。ラブコメであるというのに、その孤独な修行を志した彼の心境に僕は感動し、作者が描く香り立つような味噌鍋の描写に、味噌鍋を食べたくなった。しかし、実を言えばもう鍋は食傷気味だ。滾るような味噌鍋への想いと、鍋自体へのノイローゼとが、火花を散らしせめぎ合う。僕はその火の粉に燻ぶりながら週末を過ごし、また仕事へと繰り出した。