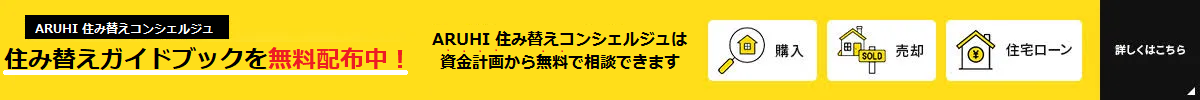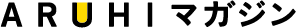アジア最大級の国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア (SSFF & ASIA)が展開している、短編小説公募プロジェクト「BOOK SHORTS (ブックショート)」とARUHIがコラボレーションし、3つのテーマで短編小説を募集する「ARUHIアワード」。応募いただいた作品の中から選ばれた10の優秀作品をそれぞれ全文公開します。
ブブブ。スマホが震える。啓太は読んでいた漫画を伏せて画面を見た。綾子からのメッセージだった。慣れてた手付きで指を滑らせ、返信する。
「今なんしよ?」
「部屋で漫画見とる」
「なんの?」
「こち亀」
「授業は?」
「今日は自主休講ばい」
綾子とは一ヶ月前に付き合い始めたばかりだ。啓太が二年生のとき、新入生の綾子がテニスサークルに見学に来たのが出会いだった。ショートヘアーが似合い、よく笑う女の子で、一目で好きになった。
なんとかして彼女をサークルに入れようと必死に勧誘し、入部後はデートの勧誘に精を出した。相手にされない日が続いたが、その年のクリスマスイブにやっと二人でのディナーにこぎ つけることができた。付き合ってから、なぜあのとき来てくれたのか綾子に聞いたところ、「そろそろ先輩が可愛そうになってきたから」と答えられたのは少しショックだった のを覚えている。
「ちょうどよか。今〇〇駅おる」
「なんで?」
「ちょっと用事で」
〇〇駅は啓太のアパートから十分ほど歩いたところにある。今学期から三年生になった啓太は、所属キャンパスが変わる関係で、三週間前に今の部屋に引っ越したばかりだ。
「部屋、行ってよかと?」
「え、今?」
「今。ヒマやろ?」
「ヒマやけど、来ても面白いことなかとよ?」
「そんなに長居せんし、ちょっと寄るだけ」
「いやええよ、駅前まで俺が行くばい」
「ケイくんの部屋に行きたか。もう向かってるから、待っとってな~」
どげんしよ、どげんしよ。綾子が来るのは嬉しい、付き合いだしてから一ヶ月間、お互いの呼び方が名字から名前に変わったくらいで、まだ手も繋いでいない二人に進展のチャンスだ。 でも、この部屋に呼ぶわけには行かない。
まだこの部屋に引っ越してきて三週間しか経っていないにもかかわらず、中はこち亀の両さんの部屋みたいに散らかっていた。
敷きっぱなしの布団を中心に、飲み終わったビールやチューハイの缶、読み終わった雑誌、スナック菓子の袋、コンビニのレジ袋が同心円状に広がっている。台所には食べてそのまま洗われていない食器がシンクに積み重ねられていて、下の方の皿は垢でヌメっている。コンロの周りにも空の、まだ少し中身が入っているものもあるが、ペットボトルが大量に並べられて おり、料理ができるような環境ではない。築三年の鉄骨3階建てアパートの最上階という、建物の新しさと高さのおかげで、こんな汚い部屋でも今の所あの黒光りする害虫が出現していないのは救いだ。コバエはいる。
とりあえず、台所の下の段の戸棚から大きめのゴミ袋を取り出し、手当り次第に燃えるゴミも燃えないゴミもごちゃまぜに突っ込んでいく。空き缶、雑誌、弁当の殻等々。
枕元のビールの500ml缶に足を引っ掛けた。空き缶ではなかった。中から黄金色の液体がドクドクと溢れだし、床に広がる。慌ててすぐに缶を立て、タオルで拭こうとするが、そのタオルが見当たらない。仕方なく、テイッシュ代わりに使っているトイレットペーパーで代用する。こぼしたビールを覆うようにトイレットペーパーを被せる。一番上の紙まで染みてきたら、 さらに被せる。あと十分足らずで綾子が到着する。
「こりゃ間に合わん」
そうつぶやくと、床に置いていたスマホを取り、一本電話をかけた。
「アパートの前、ついた」
綾子からそう届くと、啓太は部屋から出て、アパートの階段から道路を見下ろす。綾子はスマホをいじっていたが、気配に気づくと顔を上げた。
「上がっといで 」
そう声をかけ手招きすると、綾子は白い歯を輝かせてニッと笑い、階段を登ってきた。
「ごめんな、急に押しかけて」
綾子は手のひらを合わせる、啓太は、ええよええよ、と答えて、201号室の部屋を開けた。